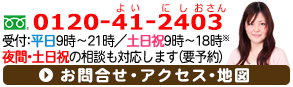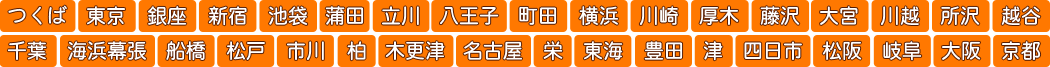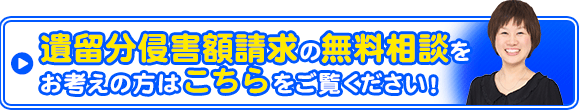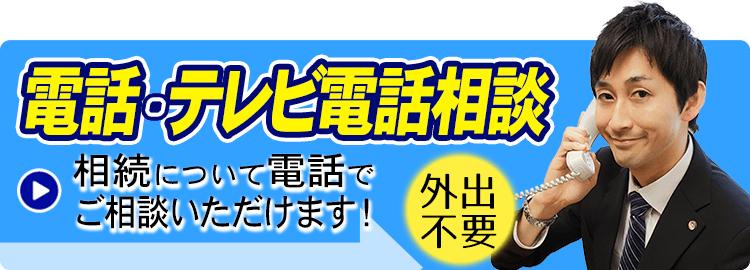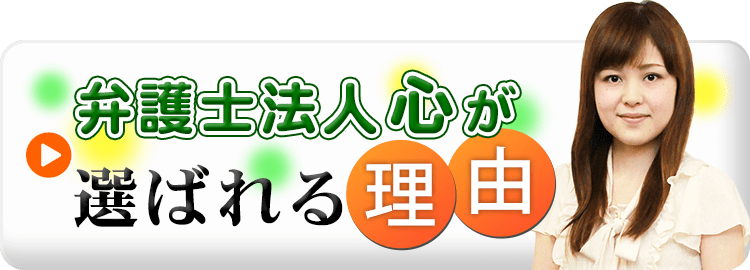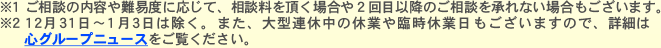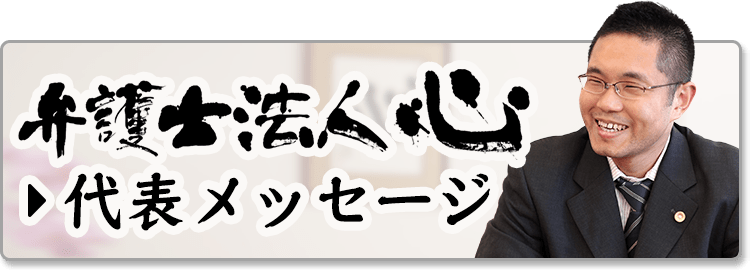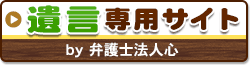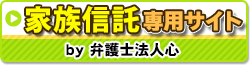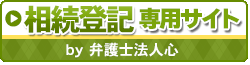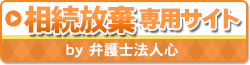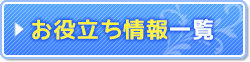遺留分侵害額請求はどうやるの?手続きや必要書類を徹底解説
遺留分侵害額請求を行う場合は、内容証明郵便の送付・支払督促・訴訟といったさまざまな手続きを行う必要があります。
それぞれの手続きには専門的な準備が必要となるため、弁護士に相談して万全の態勢を整えるのが望ましいといえます。
このコラムでは、遺留分侵害額請求の仕方や必要書類などについて詳しく解説します。
1 遺留分侵害額請求とは?
最初に民法改正前の「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」との違いや計算方法、消滅時効について簡単に触れておきます。
⑴ 遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
相続法改正前には、「遺留分侵害額請求」は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害された遺留分相当の金銭ではなく、実際に遺留分の対象となる相続財産そのものの返還を請求することができました。
しかし、たとえば、遺留分減殺請求により不動産が共有状態になってしまうことで、売却や使用をめぐって相続人間でトラブルが発生することもあり、相続問題の終局的解決につながらないという問題がありました。
そこで、改正された民法では、遺留分侵害額請求は、相続できる財産が遺留分額に不足する場合において、不足額相当の金銭を遺留分侵害者に請求することになりました(民法1046条1項)。
⑵ 遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額は、基礎財産に遺留分割合をかけた「遺留分額」を算出したうえで、そこから実際に相続・遺贈・贈与によって得た財産を控除することによって計算します。
遺留分侵害額に関する計算の詳細については、以下の記事をご参照ください。
⑶ 遺留分侵害額請求の消滅時効
遺留分侵害額請求権には、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」という消滅時効が設けられています(民法1048条前段)。
したがって、消滅時効が完成する前に請求を行うことができるようにするためには、早めに検討・準備に着手することが大切です。
2 遺留分侵害額請求方法|内容証明郵便の送付
遺留分侵害額請求を行う場合、まず相手方に対して内容証明郵便を送付するのが一般的です。
⑴ 内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便局が内容・差出人・受取人・差出日などを証明してくれる郵便をいいます。郵便局による証明がなされることから、一般的に証拠価値が高いとされています。
遺留分侵害額請求では、時効との関係で郵便の到着日を記録する必要があるため、内容証明郵便の利用時に「配達証明」のオプションを追加することで配達が完了した日がわかるようにして、配達証明付き内容証明郵便で請求するのが適切です。
⑵ 内容証明郵便の送付により消滅時効の完成が猶予
前述のとおり、遺留分侵害額請求権には1年という短い時効があります。
しかし、内容証明郵便によって相手方に対して遺留分侵害額の支払いを催告すると、消滅時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条1項)。
この6か月の猶予期間の間に準備を整え、訴訟による裁判上の請求か調停を行えば、基本的に消滅時効が完成することはなくなります(民法147条1項1号、3号)。
そのため、遺留分侵害額請求を行う場合、まずは内容証明郵便を送付して時間を稼ぎ、その後に詳細な検討や訴訟準備を行うという実務が一般的です。
⑶ 内容証明郵便の謄本には決まった書式がある
郵便局に内容証明郵便の送付を依頼する場合、内容文書(受取人へ送付するもの)の他に、差出人の側で謄本を2通作成する必要があります。
この謄本は、かなり厳密に書式が決まっているので注意が必要です。
郵便局に行かなくても使える電子内容証明サービスとひな形の利用も検討しましょう。
書式に不備がある場合には、内容証明郵便の配達を受け付けてもらえない可能性があります。
不安な場合には、弁護士に作成を依頼するとよいでしょう。
3 遺留分侵害額請求方法|調停を検討
内容証明郵便より遺留分侵害額を支払うよう催告を行っても相手方が応じない場合には、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることを検討しましょう。
⑴ 調停手続きの流れ
調停手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。
- ① 調停の申立て
-
遺留分侵害額の調停申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。
申立ての際には、(2)で解説する必要書類等を提出しなければなりません。
- ② 主張書面・証拠の準備、提出
-
調停期日において効果的に主張を展開し、調停委員に言い分を理解してもらうため、遺留分侵害があったことに関する主張内容を記載した書面と、主張する事実があったことを示す証拠を提出するのが効果的です(必須ではありません)。
- ③ 調停期日
-
調停期日では、調停委員が当事者の言い分を個別に聴取し、妥協点を探りながら調停案への合意を目指します。
話し合いがまとまらない場合は、当事者の意思を確認しながら次回期日を設定するかどうかを決定します。
- ④調停成立or不成立
-
当事者同士が調停案に合意できれば、調停は成立し、調停案の内容が当事者を拘束します。
一方、調停案への合意が成立しなければ、調停は不成立となり、訴訟手続きへの移行を検討することになります。
⑵ 調停申立ての必要書類等
調停を申し立てるのに必要となる書類及び費用等は、以下のとおりです。
- •申立書およびその写し(相手方の数の通数)
- •被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- •相続人全員の戸籍謄本
- •遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- •遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料など)
- •収入印紙1200円分
- •連絡用の郵便切手
この他、被相続人と相続人の関係により、追加で戸籍関連書類が必要な場合があります。
連絡用の郵便切手の金額は、家庭裁判所の窓口で確認しましょう。
4 調停不成立の場合は訴訟提起
調停が不成立となった場合は、訴訟手続きの中で遺留分侵害額請求を争うことになります。
なお、遺留分の請求は原則として調停を経なければ訴訟提起できないとされていますが、全く話し合いの余地がないなど、例外的に調停を経ずに訴訟を行うことが認められる場合もあります(家事事件手続法257条)。
以下では、訴訟手続きの基本的な流れと、準備すべき必要書類等について解説します。
⑴ 訴訟手続きの流れ
訴訟手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。
- ① 訴状の提出
-
訴訟を提起する場合、まず裁判所に訴状を提出する必要があります(民事訴訟法133条1項)。
訴状には、遺留分侵害額請求の内容や、請求を基礎づける要件事実を記載します。
- ② 準備書面・証拠の提出
-
法廷で開催される口頭弁論に備えて、遺留分の侵害が発生した具体的な経緯などを記載した準備書面を作成します。
それと併せて、訴訟で主張する事実を立証するために必要な証拠を集め、裁判所に提出します。
相手方(被告)からは、答弁書が提出されます。
- ③ 口頭弁論
-
第1回口頭弁論期日では、訴状、答弁書および準備書面に記載された内容の陳述を行います。
その後、おおむね1,2か月おきに口頭弁論期日が指定され、当事者双方が主張・立証を展開します。
- ④ 和解勧告
-
訴訟の途中で、裁判所が当事者双方に関して和解を勧告する場合があります(民事訴訟法89条)。
裁判所が提示した和解案を当事者双方が受け入れた場合には、「裁判上の和解」が成立して訴訟は終了します。
裁判上の和解が成立した場合、確定判決と同一の効力を有する和解調書が作成されます(民事訴訟法267条)。
- ⑤ 判決
-
裁判上の和解が成立しないまま、口頭弁論における主張・立証が出尽くしたと判断された場合、裁判所は判決を言い渡します(民事訴訟法243条、250条)。
- ⑥ 判決の確定
-
判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴することができます。
控訴期間に適法な控訴が行われなかった場合、判決が確定します。
請求を認める判決が確定した後は、強制執行により財産を差し押さえることができるようになります。
⑵ 訴訟提起の必要書類等
訴訟を提起するのに必要となる主な書類は、以下のとおりです。
- •訴状の正本および副本
- •証拠書類の写し
- •収入印紙
- •郵便料
収入印紙と郵便料の金額は、裁判所の窓口で確認できます。
なお前述のとおり、上記以外に、主張内容に応じて準備書面を作成する必要があります。
5 遺留分侵害額請求についてのよくある質問(FAQ)
•遺留分権利者が未成年者の場合はどうすればいい?
遺留分権利者が未成年者であっても、ご自分の遺留分を請求できることに変わりありません。
しかし、遺留分侵害額請求は法律行為であるため、未成年自身が行うことはできません。
未成年の親権者が同じ被相続人の相続人となっていなければ、親権者が未成年者の代わりに遺留分侵害額請求をすることが可能です。
一方、未成年の親権者が同じ被相続人の相続人となっている場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、遺留分の請求は特別代理人が行うことになります。
なお、この場合の遺留分侵害額請求の消滅時効は、法定代理人や特別代理人が「相続開始」と「遺留分が侵害されている」事実を知った時から1年となります。
•遺留分侵害額請求は自分でできる?
ご自分の遺留分が侵害されている事実を把握することはさほど難しくないかもしれません。遺留分の侵害を知った相続人が、内容証明郵便の送付までをご自分ですることは可能でしょう。
しかし、請求後、ご自分の遺留分がいくらになり、相手方にどれだけ請求できるのかを把握することは難しいでしょう。というのも、遺留分は民法に則って正しく計算しなければならないからです。
その上、遺留分権利者と遺留分を請求される側とで、基礎財産の価額評価について合意に至ることは難しく、この点でも専門的な知識が必要になるのです。
さらに、訴訟になると、残念ながら弁護士以外では、対応が難しいと言えます。
遺留分の請求でお悩みの方がいらっしゃいましたら、一刻でも早く弁護士に相談することをおすすめします。
6 遺留分侵害額請求を行うなら弁護士に相談を
遺留分侵害額請求は、内容証明郵便だけではなかなか払ってもらえず、また金額についても争いになりやすいため、容易に解決しないことも多いのが現実です。
最終的には訴訟に発展する可能性もあり、訴訟準備には専門的な対応が要求されます。
したがって、遺留分侵害額請求を検討している場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人心では、遺留分侵害額の計算、内容証明郵便の作成・交渉、調停や訴訟の準備に至るまで、適切な遺留分侵害額請求を行うことができるようにサポートいたします。
ご依頼者様の時間や労力、精神的ご負担も軽減できるかと思います。
遺言書の内容や贈与にご不満をお持ちの方は、当法人までご相談ください。